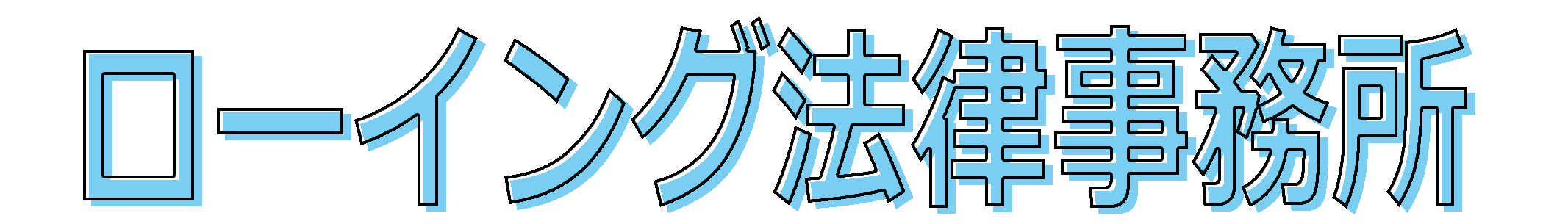「固定残業代」という制度は、労働者・経営者のいずれの立場でも、非常に注意しておくべき制度だと思います。
固定残業代とは、労基法37条に定める計算方法による割増賃金を支払う代わりに、固定の定額の残業代を支払う制度をいいます※1。皆さんの中にも、固定残業代で支給されている方もいるのではないでしょうか。
固定残業代の制度がとられている場合でも不足分があれば追加で請求可能ですが、それに加えて、固定残業代の有効性が争点になりうるということにも注意が必要です。
説明のため、簡略化した例をあげます。ある労働者の基本給が32万円、A手当が8万円、月の通常の労働時間が160時間、時間外労働時間が40時間というケースを考えます。割増率は労基法37条のとおり1.25倍とします。
①A手当が固定残業代として認められる場合
320,000円÷160時間=時給2,000円 となるため、
2,000円×1.25×40時間=100,000円 が割増賃金の総額となり、
100,000円-80,000円=20,000円 が未払残業代になります。
②A手当が固定残業代として認められない場合
400,000円÷160時間=時給2,500円 となるため、
2,500×1.25×40時間=125,000円 が割増賃金の総額となり、これがそのまま未払残業代になります。
このように、固定残業代の合意が有効か否かは、時給を定めるという点と、一部または全部が支払済みとされるかという点の2つで関わってくるので、未払残業代の総額に非常に大きな影響を与えます。
私は、労働者の代理人として法人に対して未払残業代の請求をしたこともありますし、会社側の代理人として労働者からの未払残業代の請求に対応したこともありますが、どちらの場合でも、固定残業代の有効性が主要な争点になることが少なくありません。
では、固定残業代が有効とされるためにはどうすればよいでしょうか。
この点については判例が蓄積されており、現在の一般的な理解としては、①当該手当が時間外労働等に対する対価として支払われていること(「対価性」といいます。)、②通常の労働時間の賃金に当たる部分と割増賃金に当たる部分とを明確に判別できること(「判別性」といいます。)の2つが要件であると解されます※2。例えば、通常の賃金と時間外・深夜割増賃金を明確に判別できなければ、②の要件を欠くことを理由として、固定残業代の支払いとして認められないことになります※3。
割増賃金をなるべく支払わないようにするなどの目的で、通常の賃金を極端に少なくして固定残業代を大きくするという方法をとるのは、得策ではありません。このような場合、判例では、会社側が固定残業代として支払っていた手当に、通常の労働時間の賃金として支払われるべき部分をも相当程度含まれていると解釈されるという理由で、判別性要件が否定され、固定残業代の有効性が否定された例があります※4。
このように、固定残業代が会社内で制度として存在していても、法的な効力が否定されることもあります。
固定残業代の制度の適切性にお悩みの経営者の方、従業員から未払賃金の請求を受けて対応を検討中の経営者の方は、弁護士に相談してみてください。当事務所であれば、会社の実情に沿ったアドバイスをいたします。
また、賃金が適切に支払われていないのではないかとお悩みの方も、弁護士に相談してみてください。未払賃金請求権の時効は3年(労基法附則143条3項)ですので、請求をしなければ過去の権利から順次消滅してしまいます。当事務所であれば、未払残業代を計算して請求するお手伝いをさせていただきます。
2024年4月15日 弁護士 矢野 拓馬
引用
※1:石嵜信憲編『割増賃金の基本と実務〈第2版〉』(中央経済社、2020年)123頁。
※2:匿名記事「判批」判例タイムズ1510号(2023年)150頁。引用部分は151頁。
※3:京都地裁平成29年6月29日判決(平27(ワ)2625号)、控訴審は大阪高裁平成31年4月11日判決(平29(ネ)1966号)。
※4:最高裁令和5年3月10日判決(裁時1811号14頁)。