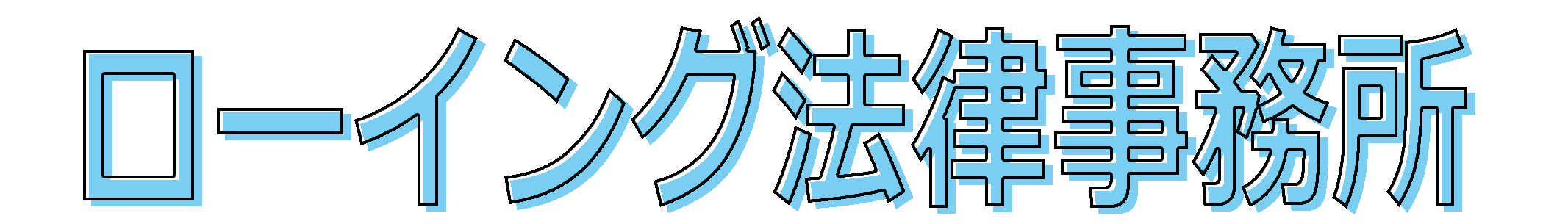皆さんは、犯罪被害に遭ってしまったとき、刑事裁判手続に参加できる制度があることをご存じでしょうか。
今回は、被害者の方が刑事裁判手続に参加できる制度である「被害者参加制度」について解説したいと思います。「被害者参加制度」とは、その名のとおり、被告人の刑事裁判の手続に、被害者の方等が参加することができる制度です(刑事訴訟法316条の33)。
対象犯罪は、殺人、傷害致死、傷害、不同意わいせつ等性犯罪、過失致死傷等の重大な事件に限られていますが、被害に遭われた方又はその法定代理人(刑訴法第316条の33第1項)が参加することができます。
被害者の方がお亡くなりになられている事件においては、被害者のご遺族の方が参加することができます。
(※今回の説明では、被害者の方等について、単に「被害者」と呼ぶことにします。)
では、刑事裁判に「被害者参加」した場合、具体的にどのようなことができるのか説明します。
- 刑事裁判の公判期日に、検察官の横に着席して、出席することができます。(刑訴法第316条の34)。
⇒ 事情によっては、被告人や傍聴席との間の遮蔽措置(衝立を設置して、被告人や傍聴者から見えないようにする措置)を取ることができます(刑訴法316条の39第4項、5項)。 - 検察官の権限の行使に関し、意見を述べることができます(刑訴法第316条の35)。
- 情状に関する証人の供述の証明力を争うために必要な事項について、証人を尋問することができます(刑訴法第316条の36)。
⇒ 対象は「情状に関する事項(犯罪事実に関するものを除く)についての証人の供述の証明力を争うために必要な事項に限られますが、証人を尋問することができます。 - 意見を述べるために必要と認められる場合に、被告人に質問することができます(刑訴法第316条の37)。
- 証拠調べが終わった後、事実又は法律の適用について、法廷で意見を述べることができます(刑訴法第316条の38)。
⇒ 「被害者論告」といい、被害者がお考えの求刑も述べることができます。
以上のことが被害者参加を行った場合にできます。被害者がご自身で対応をすることができますが、弁護士に依頼すれば、上記について、弁護士のサポートを受けることができます。
特に、上記5の「被害者論告」については、どのような意見を言えばよいのかなかなかイメージが付かないと思います。そのような場合、弁護士に依頼していただければ、被害者論告の内容について、一緒に検討することができます。
当事務所では、被害者参加される方に被害者参加弁護士経験のある弁護士が相談から事件終了までサポートすることができます。
お困りの際には、是非お問い合わせください。
令和7年5月7日 弁護士 徳山 紗里